たくさんの動物と過ごす生活は楽しそうで憧れますが、自分の健康状態が思わしくなくなったり、使える時間と使えるお金、土地と建物のキャパシティを超えてしまうと楽しい生活は維持できなくなります。できる範囲で複数動物を飼育すること自体は問題ありませんが、限度を超えると劣悪多頭飼育者(アニマルホーダー)となって多頭飼育崩壊を引き起こすおそれがあります。

劣悪多頭飼育者(アニマルホーダー)を防ぐために、『環境省_平成21年度 動物の遺棄・虐待事例等調査報告書』を参考にまとめてみました。
日本語で言う劣悪多頭飼育者を米国ではアニマルホーダーと呼びます。ホーダー(hoarder)とは専門用語で、ごみや物を捨てられず集めてしまう精神病理がある人に対して使われています。
アニマルホーダーの定義は以下のとおりです。
1. 多数の動物を飼育している(頭数の基準はないです)。
2. 動物に対し、最低限の栄養、衛生状態、獣医療が提供できない。
3. 動物の状況悪化への対応ができない。
4. 環境悪化に対応できない。
5. 本人や同居人の健康や幸せにマイナス効果が生じていることに対応ができない。
上記の定義に該当する場合がアニマルホーダーであると考えられ、何頭飼っていればアニマルホーダーに該当するか明確でないことがポイントです。
アニマルホーダーに見られる共通の特質は、動物に対して避妊、去勢の手術を行わず、自家繁殖により増えていくことです。犬よりもどちらかといえば猫がひどい状況だとされており、多頭飼育のためそれぞれの個体に手を掛けることができず動物病院にも連れて行けません。
どのような状態がアニマルホーダーなのか、特徴を具体的に紹介します。
1.収入や時間のほとんどを動物に使う
しかし、十分な栄養や医療などの提供は行わないので、多くの動物が劣悪な環境で過ごす状態となります。
2. 動物好きをアピールしており周囲にサポートする人がいる
行政から動物を引き取るケースも見られます。周囲には「動物が好きな人」と映るため、サポートする人がいます。
3. 動物以外も収集する傾向がある
ごみや不用品なども集めるという特徴があります。その結果、アニマルホーダーの家は、ゴミ屋敷状態になる傾向があります。
4. 新しい飼い主探しをしない
「自分しか世話できない」「他人には懐かない」というように「譲渡できない理由」を自分で作る傾向があります。愛護団体や行政に不信感を持ち、サポートを受けようとしないのも、アニマルホーダーに多い特徴です。
保護した動物が安心して暮らせるように、動物保護活動家が新しい飼い主を探す行為とは真逆に見えます。
5. 病気に対する関心が薄い
「生きていること=大丈夫」といった考え方をしている場合が多く、動物が病気になっても、適切な医療を受けさせません。動物は病気のまま、治療されず放置されます。
6. 何度も繰り返す
家族や行政が動物を取り上げたとしても、同じことを繰り返します。動物を取り上げるだけでは根本的な解決にはならないということがこの問題の根深いところです。

アニマルホーダーになる代表的な原因は下記に上げますが、人によって異なるようです。
1. 強迫性障害(OCD)
2. 近親者の死を始めとする重大な喪失
3. 認知症
4. 精神疾患
特に関係が深いと考えられているのが、強迫性障害(OCD)です。その患者のうち約2割に、動物に限らずホーディングの症状が見られますが、必ずしもアニマルホーダーになるわけではありません。患者の中には、自分で症状に気がついて治療を受ける人もいます。
※強迫性障害とは
実際にはありえない事象や状況に不安感を覚え、その不安に本人はバカバカしいと分かりつつも過度にとらわれ、それを解消するために一見無意味で過剰と思われるような行動を繰り返す病気です。具体的には、『家の施錠』、何度も確認したにもかかわらずかけたか不安に思って繰り返し家に戻るような行動を指します。生活上のさまざまなことが不安になり何度も確認する行動は誰にでも多かれ少なかれあるものですが、強迫性障害は“強迫観念”と“強迫行為”が続き、支配されることで日常生活に大きな支障をきたす病的な状態を引き起こします。
アニマルホーダーは、基本的に自分自身の状態を病気の症状だとは考えていません。治療には認知行動療法を繰り返していく必要がありますが、自覚がないアニマルホーダーに対する治療は困難です。
多頭飼育が崩壊している状況、あるいはそれに近い状況を確認した場合は、それに気づいた第三者のアプローチとして、動物愛護センターや保護団体、ボランティア団体に相談する方法があります。また地域包括支援センター、社会福祉協議会など、福祉関係の機関への相談も必要です。
動物好きで多頭飼育傾向にある方は、ぜひ崩壊(アニマルホーダー)にならないために気をつけていただきたいと思います。そのためには、常に以下のことを確認して行動してください。
1.動物のためにも、自分のキャパシティを決めましょう
動物を飼うには、十分な栄養、適切な医療、清潔な環境が必要です。十分な栄養と適切な医療には、費用もかかります。また清潔な環境を保つためには、ある程度の広さも必要です。用意できることを見極め飼育ができる限度を決めましょう。限度いっぱいではなく、余裕を持って飼育ができることも重要なことで、多頭飼育崩壊(アニマルホーダー)することを防げます。
2.飼育する動物の避妊や去勢を必ず行いましょう
3.ちょっと増えたかな、維持がたいへんだと感じたら相談しましょう
現在でも、飼育している動物に心と体で十分尽くしているのです。それ以上の動物の抱え込みはご自身の負担と動物へのストレスになります。困ったときは行政、愛護団体などに相談してください。

快適に過ごせない劣悪な環境下に、どんどん動物を集めてしまうのがアニマルホーダー(多頭飼育崩壊)です。その状況は動物だけでなく、本人や周囲の人も不幸にします。本人が自覚するのは難しいため周囲の注意も重要ですし、動物を飼っている方々が、まず「アニマルホーダー」を意識して、日々考え、修正し、動物とのよりよい関係を作っていってください。


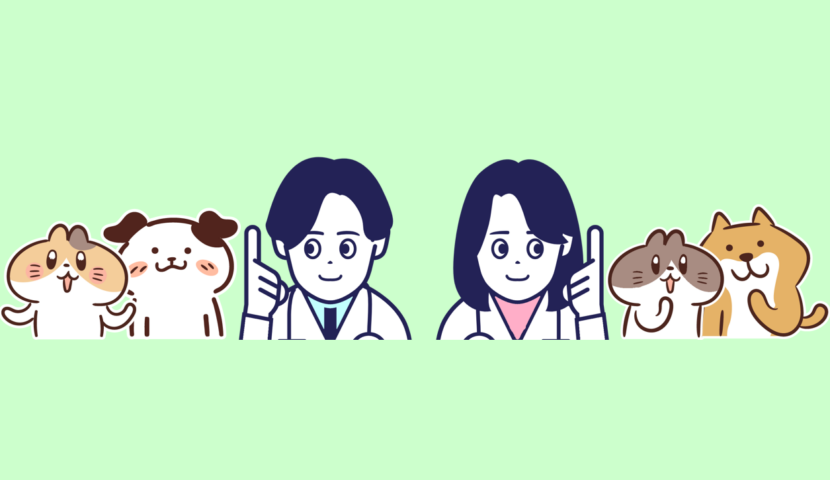
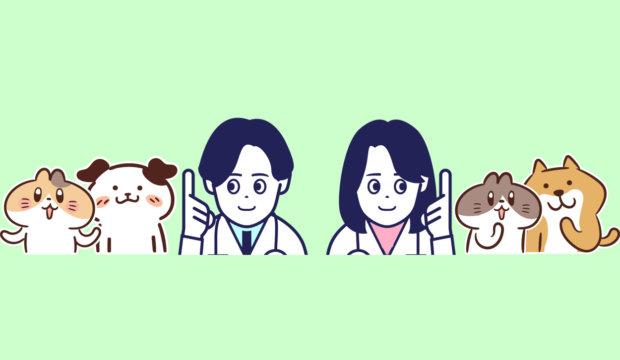
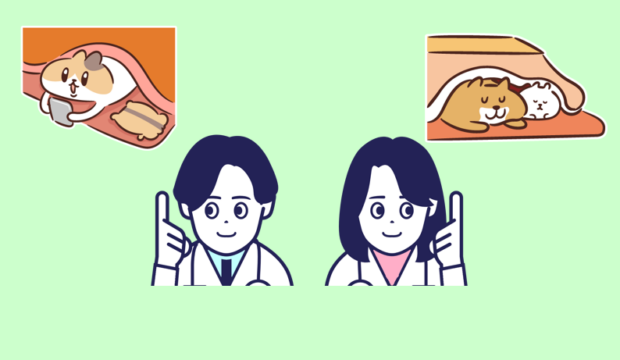


コメント