SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略称であり、日本語で“持続可能な開発目標”という意味になります。読み方は、「エスディージーエス」ではなく、「エスディージーズ」で、正式名称の単語の頭文字と、最後にあるGoalsのsを合わせています。
SDGsの始まりは2015年9月です。2016年から2030年の15年間で達成すべき“世界共通の目標”として、2015年9月に国連で開催された持続可能な開発サミットで国連に加盟している全193カ国によってSDGsが採択されました。
発展途上国・先進国と国の状況を問わず、地球上のほぼすべての国が採択した国際目標であるため、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。
SDGsには、17種類の目標と、それらの目標を達成するための具体的な169個のターゲットに加え、さらにその下に232個のインジケーター(指標)があります。世界各国が、SDGsの期限である15年間で全17種類の目標達成に向けて行動していくことで、2030年以降も“持続可能な社会”を実現させ続けることをSDGsは目指しています。

SDGs 17種類の目標一覧
1貧困をなくそう
2飢餓をゼロに
3すべての人に健康と福祉を
4質の高い教育をみんなに
5ジェンダー平等を実現しよう
6安全な水とトイレを世界中に
7エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8働きがいも経済成長も
9産業と技術革新の基盤をつくろう
10人や国の不平等をなくそう
11住み続けられるまちづくりを
12つくる責任つかう責任
13気候変動に具体的な対策を
14海の豊かさを守ろう
15陸の豊かさも守ろう
16平和と公正をすべての人に
17パートナーシップで目標を達成しよう
SDGsの17目標は、社会(1-6)・経済(7-12)・環境(13-15)の3分野と、各分野と横断的に関わる枠組み(16-17)に分けられます。
SDG’sとペット業界・畜産業との関わりを見ていくと、『12つくる責任つかう責任』に関係しています。
ペット産業おいても持続可能な生産と消費を考慮しなければなりません。このビジネスにおいて、「産業が成長する程、人もペットも幸せになる」というCSV(Creating Shared Value)の考え方をベースに据えることが重要であり、その視点で求められる責任とどのように果たしていくかを考えていきます。

【つくる責任(生産する側)】
●法令遵守(動物愛護、環境保全)
●健康管理(個体管理、特に繁殖適の母体)
●適正な繁殖(回数、品種の永続性を考慮した品種選択)
●適正な環境(広さ、清潔・清掃)
●適切な飼養(栄養、新鮮な水、体の手入れ)

【つかう責任(購入し飼育する側)】
●不妊去勢手術の実施適正な繁殖、適正に飼育された動物を購入し飼う
●適正な環境(広さ、清潔・清掃)
●適切な飼養(栄養、新鮮な水、体の手入れ)
●法令遵守(動物愛護、環境保全)
次に、SDG’sと畜産業が「つくる責任つかう責任」の視点からどのような役割が求められるかを明確にします。
【つくる責任(生産者の責任)】
●持続可能な畜産
畜産経営者は、動物の飼育や育成において環境への影響を最小限に抑えることを考慮しなくてはならない。
資源(土地、生産飼料、購入飼料、生体、排泄物も含め)を効率的に利用して、廃棄物の適切な処理、エネルギーの節約などを実践し、持続可能な畜産経営を目指す。
●動物福祉
畜産経営者には、動物の健康と幸福を考えることも必要で、適切な飼育環境、栄養、医療ケアを提供し、動物のストレスを最小限に抑えることが求められます。
【つかう責任(消費者の責任)】
●持続可能な食事選択
消費者は、畜産製品を選択する時に、環境への影響や動物福祉を考慮すべきで、エシカルな畜産業者からの製品を選ぶことや、肉の代替品(植物由来のプロテインなど)を検討することが重要です。
持続可能な畜産業は、地球環境と社会に貢献するために不可欠な産業です。私たち消費者一人ひとりが価格だけではなく、その生産背景や意味などをよく理解したうえで選択することが、畜産業の取り組みを支えていくと思います。



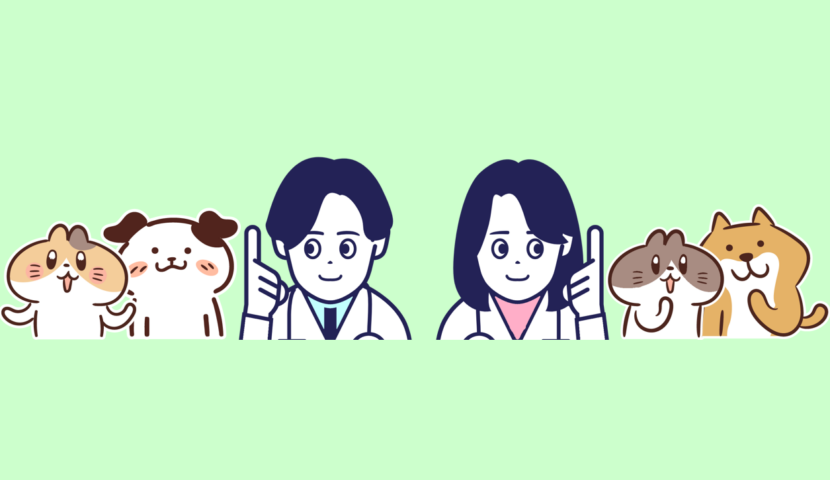
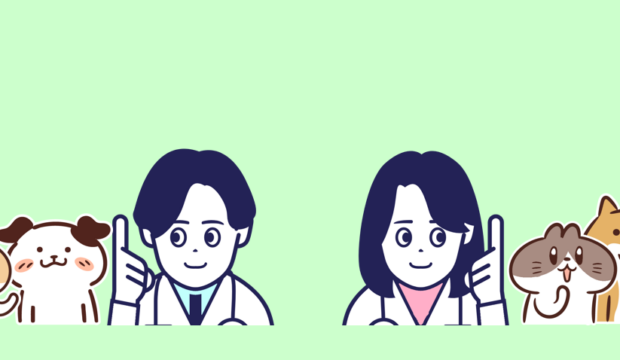
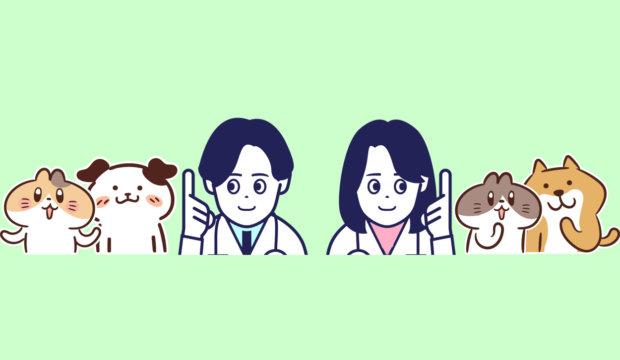


コメント