犬を飼っている高齢者は長生き傾向にあることが統計的なエビデンスが示されている。自分の世話だけではなく、ペットの世話をすることや散歩することが運動機能の低下を軽減に結びついていると考えられる。ペットとの暮らしは精神的にも充実したもの、生きがいにもなっているのだろう。
一方で、高齢者の独り身世帯でたくさんのペットを抱え込んでしまったが、その問題が潜在化し、周囲の関係者が気づいたときには悲惨な状況になっている犬猫の多頭飼育崩壊のケースも多い。このようなケースになることを恐れて、民間団体や行政機関は犬猫の譲渡に年齢制限を設け、制限を超える場合は引き続き飼養する者がいることを確認している。高齢者が犬猫の譲渡を受けることはハードルが高くなっているため、ペットを飼うのを諦める方もいる。

ペットを飼うにはそれ相応の責任は生じるが、自分で身の回りのことができる方がペットを自由に飼えないというのは不自由ではないかという疑問が生じる。また、今の日本では単身世帯もどんどん増えている。単身者がペットを飼うといろいろと心配事は出てくるが、そういった方々ほどペットを飼って癒やされたいという気持ちを持っているのかもしれない。
高齢でも、独り身でも、障がいがあっても、「誰もがペットを飼える世の中」があるべき姿ではないだろうか。誰でもペットを飼うことができ、もしもの時に助け合えるペット飼育の共助の仕組み(社会的なフレームワーク)ができないかと思う。獣医師が定期的に訪問しペットの体調を確認し、問題があれば治療する。民生委員や包括支援機関の担当者は、飼い主さんの健康上の問題で飼育の継続に支障がうかがわれる場合は、本人を交えて関係者で協議する。そして、ペットを預かるか、ペットシッターを手配するなどの対応を決める。ペットが預かりになってもたまに会うことができるなど本人の希望に沿った対応ができると良い。

健康上の問題で飼えなくなったペットを継続飼養する施設や協力ボランティアも必要になってくる。民間、個人、行政の人手と施設を想定するが、動物のお世話は長期休み中の小中高生のボランティアも期待できるかもしれない。ペットを個人で抱え込む飼い方ではなく、犬や猫の命を世代間でつないでいくような社会になればよい。
いつの日か野良犬と野良猫がいなくなり、屋外にいる犬と猫は迷い犬と迷い猫だけとなるような時代になれば、飼い主とペットの情報はより高度化した仕組みで管理されるだろう。理想の状態になるまでにどの位の時間がかかるか予想もできないが、それまでの間は、行政機関(動物愛護と包括支援)と民間保護団体、個人の動物愛護協力者、民間企業が様々な取り組みにトライし、少しずつ社会の仕組みが変わっていくと思われる。いくつになっても、単身でも、障がいがあっても、心置きなくペットと楽しく暮らせる世の中になってほしい。


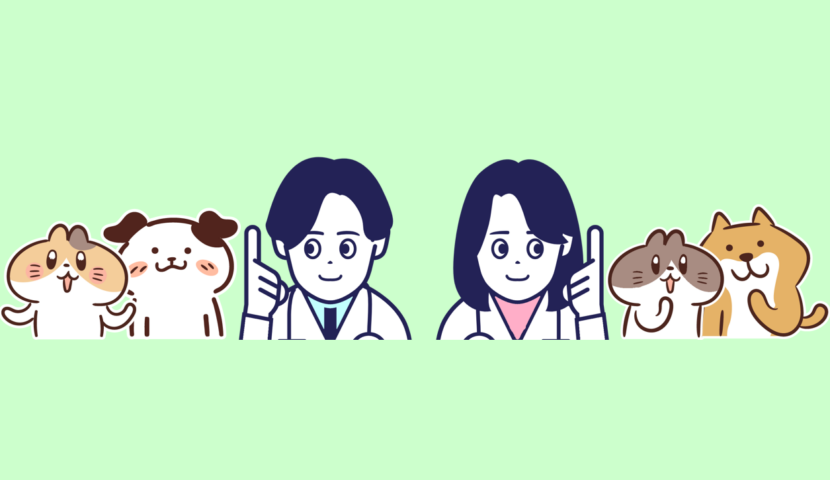
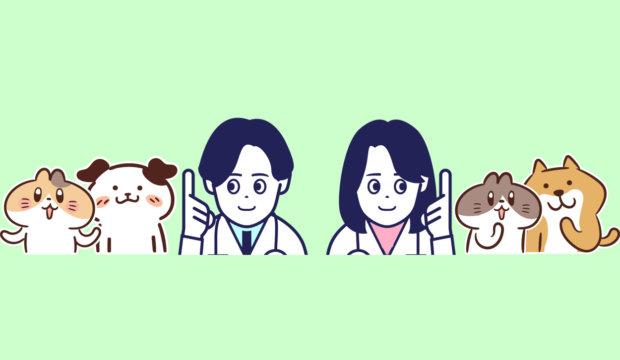
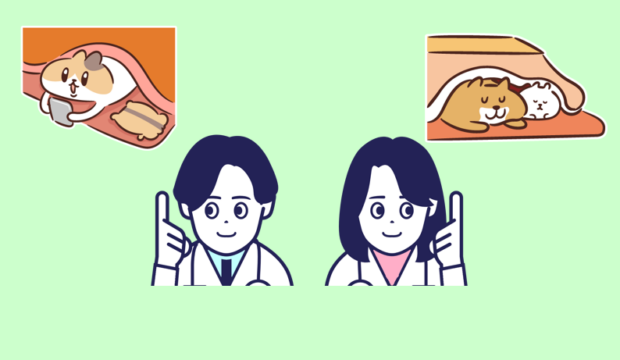
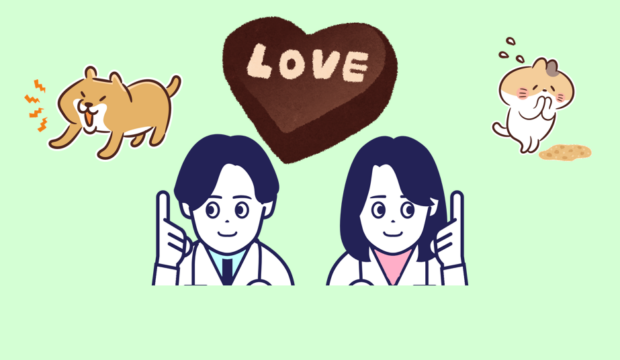


コメント