<犬が歳をとったら、まずこんな兆候が見られます>
■加齢(老化)の兆候として「目や耳が悪くなる。筋力が低下する。病気になりやすい。反応が鈍くなる(脳の老化)。」があります。
■具体的には、身体機能が衰え、今までできていた排泄などの日常生活や家族とのコミュニケーション等、いろいろなことが上手くできなくなり、「あれっ」と感じることが増えます。
■小型犬・超小型犬は11歳以上、中型・大型犬は8歳以上、超大型犬は6歳以上が高齢期の目安と言われます。犬によって差はありますが確実に老化は始まります。
■犬にもヒトの認知症に類似した「認知機能不全症候群」という病気があり、介護を必要とする場合があります。
<老化に伴い気づきが増えます>
シニア犬になると、飼い主の指示に従わない、反応が悪い・鈍い(オスワリやオテをしなくなる)、動かない、寝てばかり、トイレを失敗するなど、飼い主さんがこれまでとの違いに気づくことが増えていきます。指示に従わなく見えるのは、人と同じで、覚える意欲や飼い主の要求に応えるモチベーション低下が起きているとみられます。
<こんなこと起きてないですか(シニア犬の認知機能不全症候群の兆候)>
犬もヒトの認知症と似た状態になることがあります。
14歳以上での発生が多く、17歳以上では半数以上に徴候がでます。その症状は、「飼い主さんの呼びかけに反応がない、夜に起きて鳴く、排泄を失敗する、意味もなくうろつく、部屋の隅っこや隙間に入り立ち往生する」などです。また頭を下げた姿勢、不安定な歩き方など外観上の兆候や視力が低下していることもあります。
以上の認知機能不全に当てはまる場合でも、他の病気が原因の場合もありますので、動物病院に相談することをお勧めします。
脳が老化し萎縮することが原因で発症し、不安やストレスなどで症状が悪化すると言われています。現在のところ認知機能不全症候群を回復させる薬はありませんが、症状を抑えるための薬物による対象療法や進行を抑える目的のサプリメント投与で状態を良くすることができます。環境を高齢犬に適したものに整え、不安やストレスを取り除くことで、症状が軽くなることもあります。
<愛犬の老化を感じたら配慮すべきこと>
加齢(老化)が始まると足腰が弱り、つまずく、滑る、転ぶようになります。
■滑りにくく、段差が少ない、転んでぶつかっても危なくない環境にしましょう。
■動きや感覚が鈍くなり、部屋の隅や隙間で身動きが取れなくなる恐れがありますので、サークル(円形がベター)で囲って行動範囲を制限するのもお勧めです。
■水、ベッド、トイレ等の場所を近くに設置すると歩行時のリスクを減らせます。
■寝ている時間が長い場合は、床ずれ防止で柔らかめの低反発マットを寝床に敷きましょう。
■シニア犬は目や耳の感度が鈍って、人に気が付かないことがありますので、声をかけて前方からゆっくり近づき触るようにしましょう。
■食事や散歩などの毎日の日課は規則的に行った方がよいです。大きな環境変化は避けてください。
シニア犬のお世話は、飼い主さんの負担も増してきます。飼い主さんがお世話しやすい工夫、ペットシーツなどの積極的利用が良いと思います
<シニア犬のフードのメニューは?>
年齢、体型、体重、現在の持病なども考慮して適切な栄養バランスのフードを与えてください。フードは毎日、規則正しく与え、一回に食べる量が減ってきたら給餌回数を増やす必要があります。DHA、EPAや抗酸化物質(ポリフェノールやビタミンE)を多く含むようなサプリメントは老化予防に良いといわれていますので、ベースのフードに追加するのも良いでしょう。
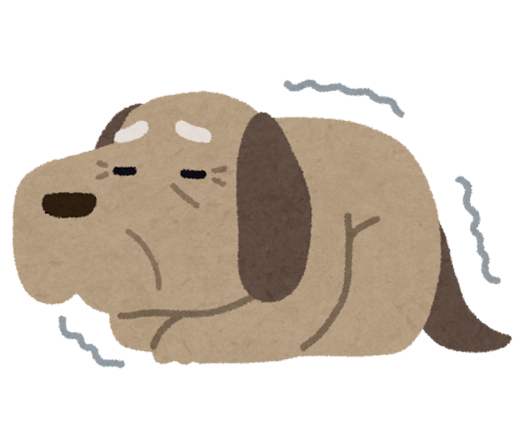
<シニア犬の健康維持は家にこもらせないこと>
■家族や他の犬とのコミュニケーション、散歩、遊びは、脳の老化を予防する良い刺激となります。外に連れて行くだけでも十分効果があります。シニア犬が嬉しい、楽しいと思うコミュニケーションを毎日取りましょう。
■シニア犬には適度な散歩が重要です。散歩は一度に長い距離を歩くより、短い距離を複数回行くのが良いでしょう。運動は脳の老化予防に効果があり、筋力維持や寝たきり予防にもなりますので積極的に行ってください。
<介護が必要になったら>
■シニア犬は低い位置に置いた食器からフードを食べることが困難になります。食器はある程度高い位置に置き、食べ易い形状のお皿で給餌してあげましょう。
■食欲低下が進み、思うように動けず自力で十分に食べられなくなったら、食事介助をしてあげましょう。フードを口に運ぶ、流動食をシリンジで与えるなどの方法があります。
■飲水は、シリンジ、スポイト、プラスチック製の水差しなどを工夫して利用しましょう。
■トイレ使用が無理になったら、犬用オムツを使いましょう。ズレ落ち防止具も販売されています。オムツを外した時に排便してくれると良いですが、できない場合はオムツを少しゆるく履かせるとよいでしょう。
■皮膚を清潔に保ち、炎症を予防するために、オムツは頻繁に交換すべきです。ワセリンや皮膚保護軟膏などを塗ってあげると、皮膚荒れが防げますので獣医さんに相談しましょう。
■さらに足腰が弱くなって寝たきりになると「床ずれ」に注意です。寝床には低反発マットや水マットなどを使用し、時々寝ている体位を変えてあげてください。体位を変えた後に、下になっていた面のマッサージをするのも床ずれ防止には有効です。
■筋力が重度に低下しても起き上がりたい、歩きたいという動作を示すワンちゃんがいます。きちんと支えないと非常に転び易いので、吊り帯など補助具を使い身体をサポートして危険の少ない場所でできる範囲で歩かせてあげてください。
<飼い主さんへ>
センターでは認知機能不全症候群になった犬の相談を受けることがあります。昼夜逆転や夜泣き行動への対応など、毎日の介護は飼い主さんの負担になるケースも少なくないと思います。
センターや動物病院、獣医さんに相談することが、症状や介護負担の軽減につながることもあります。そして、なにより家族で状況を共有し、介護を協力しながら、長く一緒に暮らしてきた愛犬を最後まで見守っていきましょう。


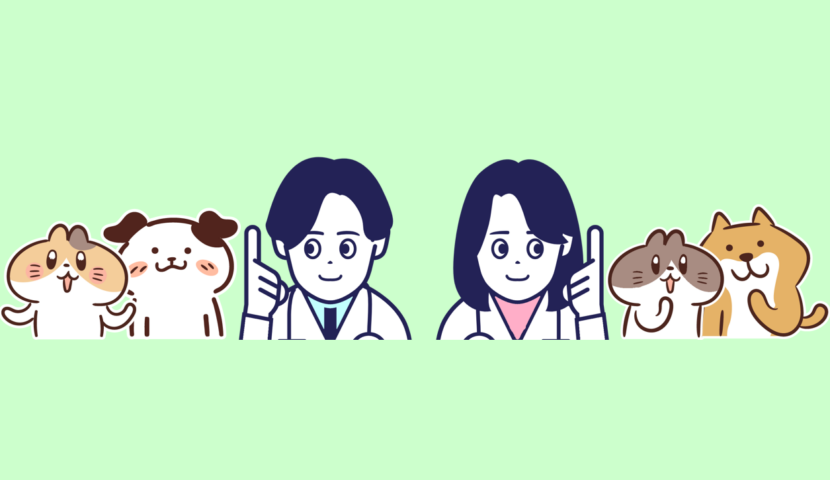
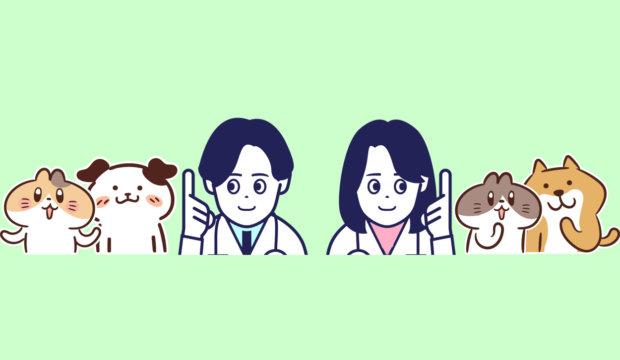


コメント